特定健診と特定保健指導
日本人の生活習慣の変化などにより、近年、糖尿病などの生活習慣病の有病者・予備群が増加しています。
病気になる前に「病気になりそうな人」を見つけることを目的として実施しているのが特定健診です。特定保健指導の対象の目安となるのがメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)です。メタボリックシンドロームとは、内臓のまわりに脂肪がたまりすぎてお腹まわりが太くなった状態に加え血糖・血圧・脂質の数値に異常がある状態のことを言います。南アルプス市国保被保険者の約3割がメタボ及びメタボ予備群であり、この状態が続くと将来的に高血圧や糖尿病、脳卒中や心筋梗塞、慢性腎臓病などを起こしやすくなることが分かっています。メタボリックシンドロームの予防や早期発見は、多様な生活習慣病を未然に防ぐことにつながります。
健診を受けることによって、自覚症状の現れない生活習慣病を早期に把握することができます。心筋梗塞や脳卒中はある日突然起こってしまったのではなく、実際は少なくとも10年以上かけて、知らない間に少しずつ生活習慣病が悪化した結果として起こります。この間に自覚症状はほとんどありませんが自覚症状に代わって自分の状態を教えてくれるのが「健診」です。年に一度は必ず健診を受けましょう。
健診を受けることで今のご自分の健康状態を知り、生活習慣を見直すきっかけとしていくことが重要です。
特定健診の結果により、保健師、管理栄養士が生活習慣改善のためのサポートをさせていただきます。
特定健診
- 検査項目(必須項目)
- 既往歴(服薬歴および喫煙習慣を含む)
- 自覚症状および他覚症状の有無
- 問診・診察・身体測定(腹囲・BMIなど)
- 血圧測定
- 血液成分検査(ヘマトクリット値、血色素量【ヘモグロビン値】、赤血球数)
- 肝機能検査
- 腎機能検査
- 血液脂質検査
- 血糖検査
- 尿検査
- 検査項目(医師が必要と判断した場合は次の事項も検査が行われます)
- 心電図検査
- 眼底検査
特定健診受診方法
・巡回健診(総合健診)
・人間ドック、個別医療機関健診
特定保健指導
健診結果により、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数により、「動機づけ支援」と「積極的支援」というプログラムの特定保健指導が行われます。
高血圧、糖尿病、脂質異常症で服薬中の方は、継続的に医師による健康管理が行われている為、特定保健指導の対象となりません。
メタボリックシンドロームの判定
腹囲が男性85センチメートル、女性90センチメートル以上、またはBMI(体重と身長のバランス)が25以上(BMI=体重[キログラム]÷{身長[メートル]×身長[メートル]})の方で、高血糖、高血圧、脂質異常、喫煙習慣など健診結果のリスクに応じて、「情報提供」、「動機づけ支援」、「積極的支援」を行います。
【メタボリックシンドロームの判断基準】
【特定保健指導の基準】

- 情報提供
健診受診者全員に健康づくりの情報提供をします。 - 動機づけ支援
メタボリックシンドロームによる生活習慣病のリスクが出現し始めている方が対象です。保健師・管理栄養士から生活習慣改善に必要な実践的な支援を行います。 - 積極的支援
メタボリックシンドロームによる生活習慣病のリスクが重なっている方が対象です。保健師・管理栄養士から3か月以上にわたって生活習慣改善に必要な継続的な支援を行います。
特定健診の結果を受け取ったら
大切なのは、健診のあと
普段、働きすぎ・食べすぎ・飲みすぎなど、体に無理を強いてはいませんか。
健診は、病気を早期に発見し、必要に応じて治療を行うと共に健康を維持するものですが、健診さえ受けていれば大丈夫、ということではありません。大事に至る前に、生活習慣など、改める必要があるものは進んで改めましょう。
生活習慣病を予防するために正しい食習慣を身につけましょう
正しい食習慣のポイント
正しい食生活のためのポイントは
・適量な飲酒 です!
バランスの良い食事
バランスの良い食事とは必要な栄養素を過不足なく摂ることのできる食事のことです。
主食・主菜・副菜(+牛乳・乳製品と果物)をそろえることでバランスがの良い食事の献立を組み立てることができます。
【主食】ごはん・パン・麺類などの料理。エネルギー源となる炭水化物(糖質)を多く含む食品です。
◇1回量 ごはんなら:女性約100~150g 男性約150~200g
食パンなら:6枚切1枚~1枚半
うどんなら:1玉
【主菜】肉・魚・卵・豆腐・納豆などを使った献立の中心となる料理。主にたんぱく質や資質の供給源になる食品です。
◇1回量 肉:約60g 魚:約60~70g 卵:1個 豆腐:100g 納豆:1パック
※1食の中でこの中のどれか1つ
【副菜】野菜・芋・海藻・きのこなどを使った料理。主にビタミン・ミネラル・食物繊維を多く含み、
体の調子を整えてくれる食品です。
◇1回量 生野菜なら両手に軽く1杯 加熱野菜(ゆでる・煮る・炒めるなど)なら片手に軽く1杯
※主食・主菜は1食に1品、副菜は2品とれるとバランスの良い食事になります。
主食・主菜・副菜の1回量はあくまで目安です。身体活動量によって適正量は異なります。
さらに、油はエネルギーを多く含むので油を使用した料理は1食に1品にすると良いでしょう。
減塩
塩分(ナトリウム)の摂りすぎは高血圧を招き、むくみや腎臓病の原因にもなります。インスタント食品や外食メニューは
塩分が多いものが多いため、控えましょう。
【1日の塩分摂取の目安量】
男性:7.5g未満 女性:6.5g未満 ※高血圧の方は6g未満
日本人の食塩摂取の現状(1日あたり)は男性11.0g、女性9.3g(平成30年国民健康栄養調査)
となっており、まだまだ減塩の心がけが必要です。
【減塩のポイント】
・調味料を使う時は、はかって使う。
・だしのうま味を効かせる。
・香り・酸味・辛味を効かせる。
・食卓に塩やしょうゆを置いておかない。
・しょうゆ・ソースなどは料理に直接かけず、小皿にとって少量つけて食べる。
・麺類の汁はできるだけ残す。
・汁ものを飲む回数を減らす。
・漬物や練り製品は塩分が多いため、食べ過ぎに注意する。
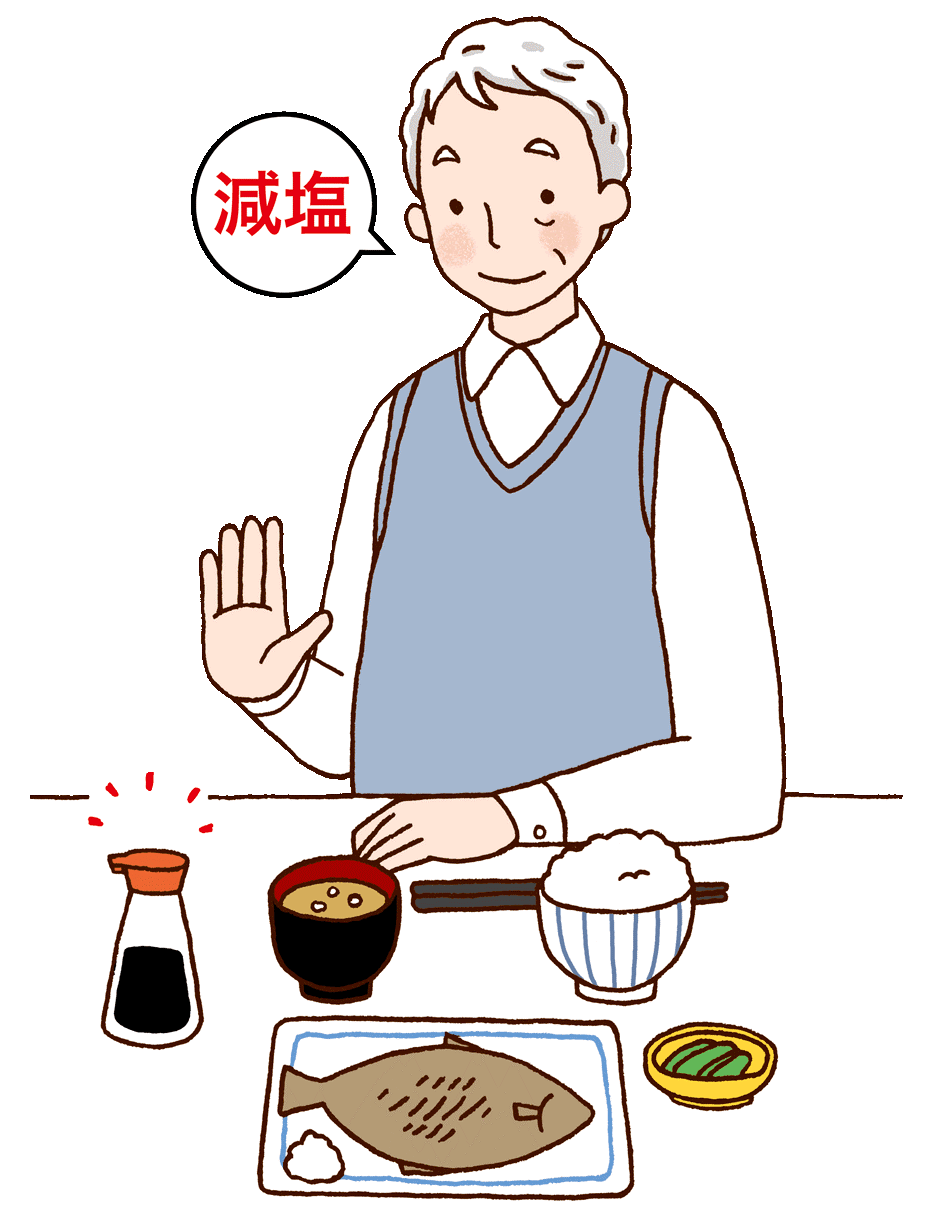
間食
菓子類や甘い飲みものには糖分が多く含まれ、食べ過ぎは肥満や高血糖を招きます。また、スナック菓子などは食塩や脂質が多いので
注意が必要です。南アルプス市民は全国や山梨県の平均に比べて血糖値が高い方が多い傾向です。(KDBシステム R2特定健診受診者結果より)
間食の食べ方を工夫して上手に付き合いましょう。
【1日の菓子・嗜好飲料の摂取量は?】200kcal程度まで
【1日の果物の摂取量は?】150g程度まで(片手のひらに乗る程度:みかん2個分・りんご(大)1/2個分)
果物にはビタミンCや食物繊維、カリウムなどの体調を整える栄養素がたくさん含まれていますが、食べ過ぎてしまうと中性脂肪が
増えるので適量を守りましょう。
【間食とうまく付き合うためのポイント】
・回数を工夫する:「間食は週○回まで」などと決めて食べ過ぎないようにする。
・種類を工夫する:糖を含む飲料ではなく、お茶や無糖のコーヒー・紅茶にする。
・量を工夫する:個包装されたものを選ぶ。一袋が大容量なら、少量を皿に取り分ける。
・時間を工夫する:夕食後、活動時間が少ない夜間、就寝前の飲食は特に太りやすいので注意する。
野菜の摂取
野菜・海藻・きのこ・こんにゃくなどには食物繊維が豊富に含まれ、食後の血糖値やコレステロールの吸収を抑える働きがありますので
不足なく食べるようにしましょう。
【1日の野菜の摂取量は?】350g(1回約120g)
☆1回量の目安☆


生野菜なら両手に軽く1杯 加熱(ゆでる・煮る・炒める)した野菜なら片手に軽く1杯
※1回の食事に野菜やきのこをメインとした副菜が2品あると1回量がとりやすくなります。
《1日の野菜摂取量のイメージ》
⇓
《1日分の野菜の献立例》
【野菜料理を1品増やすコツ】
・具だくさんの汁ものにする。
・コンビニのサラダを追加する。
・弁当に野菜のおかずを1品加える。
・カップスープに野菜を加える。
・前の晩に作り置きをして、朝食にも野菜をプラスする。
コンビニやスーパーで売っているカット野菜・冷凍野菜を利用すれば手軽で無駄なく使えます♪
適正な飲酒量
過度の飲酒は高血圧・高血糖・中性脂肪の悪化要因になります。肝臓に負担がかかり、気づかないうちに重症化していることも。
ほどよく付き合い、適量で楽しみましょう。
【1日のお酒の適量は?】純アルコール量20g以内(女性はこの1/2~1/3量が目安です)
【純アルコール量20gの飲酒量】
・ビール:中ビン1本・中ジョッキ1杯(500ml)
・日本酒:1合(180ml)
・焼酎(25度):100ml
・ウイスキー・ブランデー:60ml
・ワイン:グラス2杯(200ml)
・缶チューハイ:1.5缶(520ml)
【上手にお酒と付き合うためのコツ】
・適量を守る。(純アルコール量で1日20g以内)
・アルコール度数の高いお酒は薄めて飲む。
・低塩・高たんぱく質のつまみを食べながらゆっくり飲む。
・週2日以上休肝日をつくる。
・たばこを吸いながら飲まない。
・生活習慣病予防についてのホームぺージ
